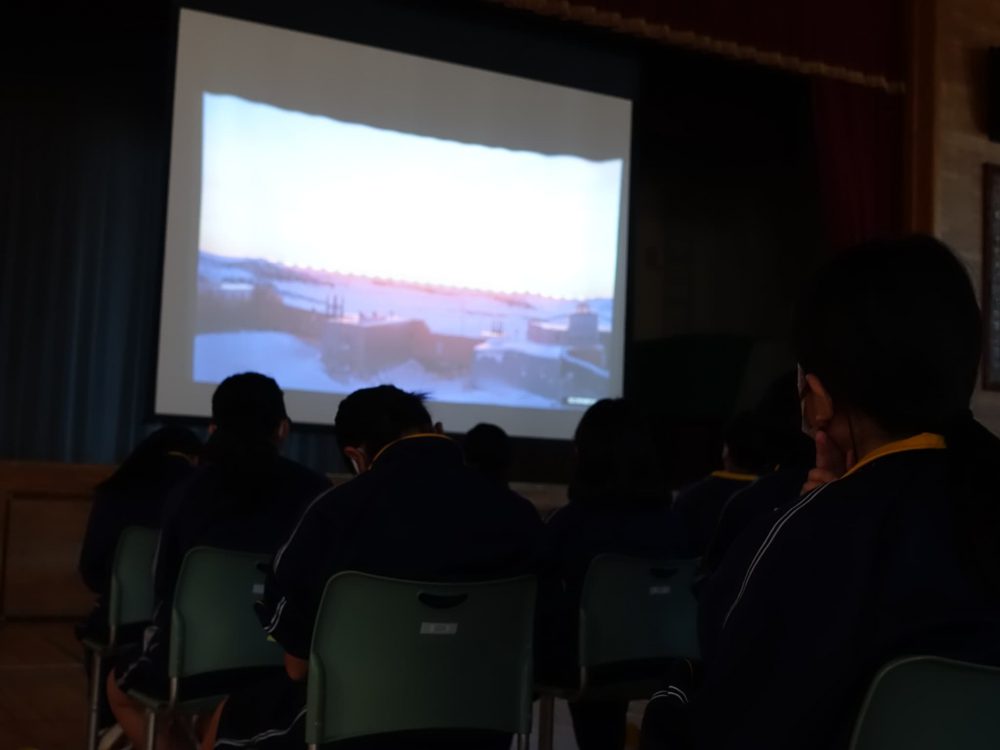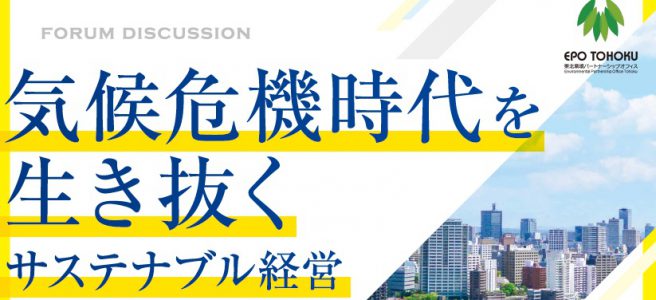MELONブログ
11/27(月)スパッと鳴子温泉自然エネルギーの取り組みを知ろう!【詳細はこちら】
宮城県大崎市を拠点に活動するNPO法人スパっと鳴子温泉自然エネルギーは、2023年2月に開催された「脱炭素チャレンジカップ2023」において、「気象キャスターネットワーク 最優秀市民・学校エコ活動賞」(全国からのエントリー数194、各省受賞団体31)を受賞されました。
鳴子温泉という地域のエネルギー資源をいかした取り組み例をまじえながら、「カーボンニュートラル」「エネルギーの地産地消」「地熱エネルギー」 「温泉」等をキーワードにわかりやすくお話していただきます。
★当日連絡先:MELON携帯 090-1377-8867
当日、体調がすぐれない場合などは無理なさらず、MELON携帯にご連絡ください。
【日時】2023年11月27日(月) 14:15~15:45
【場所】Café gutto(大崎市鳴子温泉字湯元27-2-2)
【講 師】
佐々木敬司(NPO法人スパっと鳴子温泉自然エネルギー 理事長)
村松淳司(東北大学多元物質科学研究所 教授/MELON 評議員)
【対 象】一般市民
【定 員】先着20名
【参加費】無料
早めに着いてランチしたり温泉に入ったりしてもよいですね。(^o^)/
【参加申込み】以下の申込フォームよりお申込みください。
⇒申込フォームはこちらから
⇒チラシのダウンロードはこちらから
【主 催】MELON
〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-45 フォレスト仙台ビル5F
TEL:022-276-5118 FAX:022-219-5713 Email:melon@miyagi.jpn.org
▲TOP
11/18(土)七北田公園・木の観察会【詳細はこちら】
木のことなら何でも知っている専門家の方のお話を聞きながら秋が深まった七北田公園をいっしょに歩きませんか。「へえ~」知らなかったことばかりで驚きの連続です。
お一人様、親子、家族での参加、大歓迎です!
【日時】2023年11月18日(土) 10:00~11:30
【集合時間と場所】9:45 集合・受付 七北田公園 都市緑化ホール前(仙台市泉区七北田 赤生津4)
【講 師】佐藤権一氏(公益財団法人仙台市公園緑地協会 七北田公園都市緑化ホール・緑の相談員)
【対 象】一般市民
【定 員】先着20名 ※親子参加大歓迎!
【持ち物】飲み物、軍手、筆記用具、雨具
【服 装】活動しやすい服装、帽子
【参加費】無料
【日 程】
9:45 集合・受付
10:00 開始
10:05 公園散策
11:25 まとめ
11:30 終了、解散
※終了後、各自、公園内でお弁当を食べてもよいですね。(^o^)/
【参加申込み】以下の申込フォームよりお申込みください。
⇒申込フォームはこちらから
※FAX(022-219-5713)でもお申込み可能です。チラシ裏面をご記入ください。
⇒チラシのダウンロードはこちらから
【主 催】みやぎ里山応援団(MELON内)
〒981-0933 仙台市青葉区柏木1-2-45 フォレスト仙台ビル5F
TEL:022-276-5118 FAX:022-219-5713 Email:melon@miyagi.jpn.org
▲TOP
SDGs環境出前講話キリバス編~仙台市立黒松小学校
11月7日(火)、SDGs環境出前講話キリバス編を仙台市立黒松小学校で行いました。4年生64名が参加しました。校庭にはプレハブ校舎が建てられていました。校舎の建て替え工事だそうです。
会場となる体育館に入ると、開放で遊んでいた5年生がケンタロさんの姿を見て寄ってきました。昨年、4年生のときに受けた講話のことを覚えていたのですね。
とても素直な4年生の子どもたちで、前半は楽しい話題に反応し、後半はメッセージをしっかりと受け取っていました。
黒松小学校第4学年での開催は、3年連続となります。これで、4、5、6年生のみなさんがキリバス編の講話を聞いたことになります。学年を超えての行動が起こることに期待しています。
▲TOP
SDGs環境出前講話南極編~岩沼市立岩沼北中学校
11月1日(水)、SDGs環境出前講話南極編を岩沼市立岩沼北中学校で行いました。1年生64名が参加しました。岩沼北中学校は、学校情報化先進校に認定されたICT活用のモデル校です。昨年度は、2年生でキリバス編を行いました。
生徒のみなさんと先生方は、南極の映像を食い入るように見ていました。南極の氷の厚さのクイズでは、みなさん、とても驚いていました。
講話後、はじめは生徒のみなさんからなかなか質問が出ませんでした。先生が「まわりの人と話し合って」と声がけしたところ、次々と質問が出てきました。
「一番おいしかったのは何ですか。」
「携帯は通じるんですか。」
「命の危険を感じたことは?」
時間が足りないくらいでした。
オゾン層回復のきっかけをつくった日本の観測隊の偉業に感動した校長先生、担任の先生方が岩沼北中学校で生徒のみなさんとともに起こすアクションに期待します!
▲TOP
11/22「気候危機時代を生き抜く サステナブル経営」開催
環境省東北地方環境事務所、東北環境パートナーシップオフィス(EPO東北)主催のセミナーのご案内です。
記録的豪雨の観測や深刻な干ばつなど、異常気象の被災と頻度は年々増加している中、
経済活動や消費者の動向にも大きな影響を及ぼし、企業がその対応に動くことは急務となっています。
気候危機に対応するため、地域脱炭素の具体的な推進に向けて各地でセクターを超えた対話と連携が始まっています。
サステナブル経営に関する背景や国際社会の動向、国内事例について学び、
気候危機による災害リスクをどう捉えたらよいのか一緒に考えてみませんか?
セミナー詳細は下記をご参照ください。
対象はみやぎの中小企業、金融機関の皆様のためのフォーラとなっておりますが、
ESG金融、脱炭素経営、地域循環共生圏等のテーマにご関心のある方はぜひご参加ください!
■開催概要(詳細はこちら)
日時:2023年11月22日(水)13:00~17:30
会場:せんだいメディアテーク 7F スタジオシアター (宮城県仙台市青葉区春日町2-1)
定員:120名(申し込み先着順)
参加:無料
■主催
環境省東北地方環境事務所、東北環境パートナーシップオフィス(EPO東北)
■共催
ストップ温暖化センターみやぎ、NPO法人環境会議所東北
■後援
宮城県、七十七銀行、信金中央金庫東北支店
■お申込み
受付専用フォームで必要事項を入力の上、お申込みください。
フォームが利用できない場合、件名を「11/22フォーラム申し込み」とし、本文に①会社名または所属先名 ②氏名(フルネーム) ③連絡先メールアドレスを明記の上、メールにてお申込みください。
【申し込み先】info@epo-tohoku.jp
■お問い合わせ
東北環境パートナーシップオフィス(EPO東北)
〒980-0014 宮城県仙台市青葉区本町3丁目2-23 仙台第2合同庁舎1F
TEL 022-290-7179
FAX 022-290-7181
E-mail info@epo-tohoku.jp
▲TOP
« 前へ
1
…
30
31
32
33
34
…
112
次へ »
MELONの旧ブログへはこちら